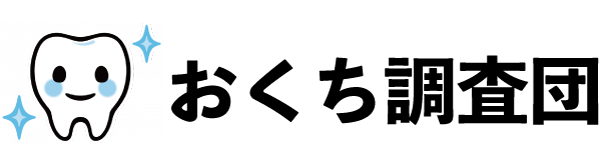歯はお顔の表情にとても影響するパーツの一つです。
白い歯は、それだけでも輝いて美しいですし、何より表情も明るくしてくれます。
ところが、そんな白い歯の表面にシミがついたらどうでしょう。
せっかくの白い歯が台無しになり、お顔の表情にも悪影響を及ぼしてしまいます。
歯のシミで悩んでいる方も多いことでしょう。
そこで今回は、歯の表面にシミを作る原因やその対策、予防法などをわかりやすく解説します。
Contents
歯にシミがつく原因
もともと白いはずの歯に、どうしてシミがついて色が変わってしまうのでしょうか。その原因を探っていきたいと思います。
脱灰によるシミ
歯の最も外側の部分は、エナメル質とよばれるものでできています。エナメル質は、骨よりも硬く、身体の中で最も硬いとも言われています。
その硬いエナメル質は、ミュータンス菌をはじめとするむし歯菌の産生する酸に弱く、溶かされてしまいます。
脱灰とは、エナメル質が酸によって溶かされ、表面の結晶構造が荒れてしまった状態を言います。
結晶構造が荒れた状態ですので、顕微鏡で見ない限りは、色の変化としてしかわかりません。
むし歯によるシミ
むし歯は、前述の脱灰された状態から更に進んだ状態のことです。
脱灰された状態では白く濃い斑点でしたが、むし歯になると、茶色い斑点になり、更に進むと黒くなっていきます。
エナメル質の形成不全症によるシミ
エナメル質は、骨とは異なり一度出来上がると、二度と形成されることはありません。
歯が顎の骨の中で出来つつある時期に、何らかの障害を受けて、エナメル質がきちんと形成されなかった状態のことです。
エナメル質がきちんと形成されない原因としては、カルシウムやリンなどの栄養素の不足から、麻疹のような高熱を発する病気、乳歯の根の先に生じた膿、妊娠中の母親の病気などいろいろあります。
歯のフッ素症によるシミ
歯のフッ素症とは、フッ素の化合物であるフッ化物を摂取しすぎたことによって、歯の表面に褐色の斑点状のシミが浮き出てくる病気のことで、昔は斑状歯とよばれていました。
これは、6ヶ月から5歳くらいの間、つまりはが顎の骨の中で出来つつある時期にフッ化物を過剰摂取した場合に起こる病気で、一旦生えた歯には何らの症状も現れません。
ですから、大人になってから過剰摂取してもフッ素症は起こりません。
テトラサイクリン歯によるシミ
テトラサイクリンとは抗菌薬のことで、肺炎や百日ぜきの治療に使われていました。
テトラサイクリン歯とは、妊娠中の母親や授乳中の母親、もしくは顎の骨の中で永久歯ができつつある8歳までの時期の子供が、テトラサイクリンをたくさん投与された副作用として歯に現れる症状のことです。
歯のシミの原因別のあらわれ方

では、歯のシミはどのような感じに現れるのでしょうか。シミの原因ごとにその症状をみていきましょう。
脱灰によるシミ
脱灰によって生じた歯のシミは、歯の表面にひときわ白い斑点状の模様として現れます。
歯は白いイメージですが、実際のところは全くの白色ではありません。
永久歯の白色は少し黄色味がかっていますし、乳歯のそれも永久歯ほどの黄色味はかかっていませんが、絵の具のような白色ではありません。
ですから、永久歯より白い乳歯であっても、脱灰によって生じた白色の斑点状の模様ははっきりと目立ちます。
むし歯によるシミ
むし歯の場合、初期の段階ですと、歯の表面に薄茶色のシミのような色模様が付きます。
一度むし歯になった歯は、自然に治ることはありません。少しずつ進行していきます。
進行に伴って、茶色がどんどん濃くなり、黒色に変化していきます。
エナメル質の形成不全症によるシミ
エナメル質の形成不全症の症状の現れ方は、歯の発育時期のどの段階で障害を受けたか、どの程度強い障害を受けたかによって、変わります。
エナメル質が出来上がる初期の段階ほど、症状が強く現れます。
具体的には、エナメル質ができない部位が生じ、本来エナメル質で覆われているべき象牙質が露出することで、茶色い歯や黄色い歯となります。
歯のフッ素症によるシミ
歯のフッ素症を起こすと、生えてきた歯の表面に褐色の斑点状の模様として現れます。
一度生えた歯に対しては、フッ化物を過剰に投与しても、歯の表面の色の変化は現れません。
あくまでも、歯が顎の骨の中で形作られている時期に限られます。
テトラサイクリン歯によるシミ
歯が出来上がる途中の段階で、歯に含まれるカルシウムとテトラサイクリンが結合し、歯に沈着していきます。
この歯に沈着したテトラサイクリンに紫外線が当たると、テトラサイクリンが酸化され、その色が大変濃くなっていきます。
その結果、歯の色が濃いグレーや茶色系の色になってしまいます。
歯のしみ対策
歯の表面にシミが生じた場合、歯科医院ではどのような処置が行われるのでしょうか。
脱灰が生じたら
脱灰によって生じた歯のシミは、基本的には経過観察となります。
確かに脱灰はミュータンス菌の酸によってエナメル質が溶かされた状態なのですが、脱灰されただけの状態なら、歯を丁寧にしっかりと磨いていれば、唾液に含まれる成分によって自然に修復される、つまり再石灰化できる可能性が残されています。
ですから、通常のむし歯治療のように削って詰めることは必要なく、フッ素を塗ったり、歯みがきの方法を指導したりします。
フッ素には、脱灰された部分を再石灰化する働きを促進する効果があります。
しかも、フッ素によって再石灰化された部分は、フッ素が取り込まれ、それ以降ミュータンス菌が産生する酸に対する抵抗力が増すことが明らかになっています。
ですから、脱灰が認められた場合は、歯みがきと同時にフッ素も積極的に利用しましょう。
むし歯になってしまったら
むし歯によって、歯の表面にシミがついた場合は、むし歯治療によって取り除きます。
小さなむし歯であれば、コンポジットレジンという歯の色に合わせたプラスチック製の詰め物で治せます。
この方法ですと、その日のうちに治療が完了します。
もう少し大きくなってくると、歯の神経を取ったり、かぶせ物をしたりする治療が行われます。
エナメル質の形成不全症だったら
エナメル質の形成不全症の場合は、形成不全の程度によって治療法が異なります。
歯の形が30%以上欠けているような場合は、かぶせ物を装着して治療しなければなりません。
前歯部の場合、保険診療でも表側を白いコンポジットレジンで覆ったかぶせ物を装着できるのですが、より美しく直したい場合は、セラミック製のかぶせ物が適しています。
奥歯の場合は、基本的に銀歯と考えていただいた方がいいでしょう。
なお、歯の変形が30%未満にとどまっているのなら、コンポジットレジンを詰めたり、後述するポーセレンラミネートベニアという方法でも治します。
歯のフッ素症だったら
歯のフッ素症により褐色の模様が入った場合に適しているのが、ポーセレンラミネートベニアという治療法です。
ポーセレンラミネートベニアとは、唇面とよばれる歯の表側を薄く削って、薄いセラミックを専用の接着剤で貼り付ける治療法です。
かぶせ物ほど歯を削らないので、しみるリスクがほとんどないのが利点です。
セラミックなので、仕上がりも非常に美しくなります。
テトラサイクリン歯だったら
テトラサイクリン歯は、症状によってはホワイトニングで改善できます。
ですが、ホワイトニングで難しい場合は、ポーセレンラミネートベニアが適しています。
まとめ
今回は、歯のシミに関して解説しました。
歯のシミは、いろいろな症状をもって現れますが、その対策のほとんどは歯科医院で行われます。
白い歯の表面にシミが生じると見た目の点からもとても目立ってしまいます。
歯のシミに気が付いたら、なるべく早く歯科医院を受診して、診てもらう事をおすすめします。